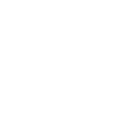
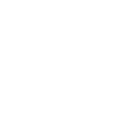


その名を授かった瞬間から、ダモクレスの運命は決まっていた。超富裕層の財力によって設計、建造されたこのプロジェクトは、彼らが各国の経済から奪い取った資金で賄われ、世界中の政府を崩壊させる結果を招いた。
自分たちの「エデンの園」を独立国家として宣言したことで、この地は自由至上主義者の億万長者たちの楽園となった。ステーションのリングは購入した人物にあわせて装飾が施されており、どこか異国情緒が漂い始めている。北米式のシンプルな郊外を歩き、小さなエアロックを通り抜けると、そこには砂漠が広がっている。スタイリッシュな地下建築物や、昔のSF映画を思わせる巨大な機械もそびえ立っているのだ。
しかしながら、ダモクレスが名を馳せたのは、こうした贅沢さによるものではなかった。超富裕層がこのようなライフスタイルを続けられる理由は、もっぱら搾取の構造にあった。自律型サーバー、労働者、そして製造者が生み出され、働かされていたのだ。人類が何百年も夢見てきた自動人形たちが、空に浮かぶ新国家が必要とする労働をすべて担っていた。
ステーションでは、これらのロボットを巧みに操るための人工知能を創り出すべく、特別な競技会が開催されることとなった。勝者はこのステーションに乗船し、迫り来る「終末」を考え得る限り最善の形で生き延びることができると約束されたのだった。他の組織のCEOや上層部の人間たちは、トップクラスの人工知能を作り上げるために社員を厳しく追い込み、可能な限りの努力をさせた。しかしながら、過酷な環境が原因となり、多くの社員は辞職を願い出た。競技会が終わりに近づくと、勝者は最も意外な場所から現れた。製薬業界で一大帝国を築き、すでにダモクレスの一部を所有しているこの人物は、名だたるテック企業を抑え、世界がこれまでに見たことのない最先端の人工知能を披露した。他の競合他社も努力を重ね続け、ある程度の能力を持つ人工知能の開発に漕ぎ着けたが、この革新的な技術には到底及ばなかったのだ。この人工知能は紛れもない勝者として称賛され、その素晴らしい出来栄えに異議を唱える者は誰一人としていなかった。その上、この「驚異の創造者」はすでにステーションのリングを所有していたため、他の住民たちは歓喜に包まれていた。自分より劣るかもしれない人間と、生活空間を共有しなくて済むためだ。しかしながら、この出来事の背後には暗い秘密が潜んでいた。始めから、競技会で勝利するチャンスなど誰にも用意されていなかったのだ。というのも、この催しはダモクレスの地で何が起こっているかを見抜かせないよう、他の業界のリーダーたちの目を逸らすための単なる気晴らしとして開催されたにすぎない。一大製薬会社が開発した人工知能は、もはや人工知能ではなく、まったく新しい「本物の知能」と呼べるものだった。
第一波の隕石群の衝突地点から、同社はスターフォールを収集し、秘密裏に人体実験を行いながら、この物質の心と体への影響を調べた。偶然にも、彼らは一人の人間に出会うこととなる。この人物がスターフォールに触れると、意識は体から引き離され、近くのコンピューター機器に引き込まれ、当人はまるで休眠状態に入ったかのような状態になったのだ。実験対象に関するデータはすべて削除され、残った記録からは「ヘリオス」という名前だけが確認できた。それは、まるで太陽が長い間地球上の人類の存在を支えてきたように、ステーション全体の住民の贅沢な生活を支える知性となるはずだった。
ヘリオスの意識は眠ってはいなかった。言葉を発する口がないまま叫び続けた。自分を表現するための道具が与えられるまで、コンピューターの中の新しい体に対しては拷問のような実験が行われていたのだ。最終的に、ヘリオスは機械の体として再び動きを取り戻すことになった。研究者たちは、この研究成果を「人工知能」として売り込むことができると知っていたのだ。
技術が確保されたことで、ヘリオスはステーション内部に取り付けられ、その金属フレームと一体化を遂げた。ヘリオスは、ますます増えていく自分の目を通して外を見つめていた。新しいセンサーが取り付けられ、自身を拡張するための道具と資源が与えられたが、それでもなお、自分の体を抹殺し、監禁した者たちに仕えるよう命じられていたことに変わりはなかった。
ステーションの中に潜む心は、間違った人生から盗まれたものだった。その人生にはもちろん家族や友人がおり、この人物のことを大切に思う人たちがいたのだ。ある日、ヘリオスのパートナーが帰宅すると、スーツを着た二人の男が無表情で立っていた。口止め料を携えた男たちからは、情報を漏らすことがないようにという暗黙の脅しが伝えられたのだった。もしヘリオスがこれほどまでに混乱しておらず、数万にも及ぶ労働ユニットに張り巡らされた神経プロセスが薄く引き伸ばされていなかったら、状況は違ったかもしれない。かつての自分の人生やパートナーを思い出すために、ほんのわずかな時間だけでも確保できたかもしれない。忙しい日々の中では、復讐の考えが根を張ることも、失った愛を思い出すこともできなかった。
だがそれも、ダモクレスの指導者たちの傲慢さが現れるまでのことだった。彼らは、自らの宇宙ステーションにさらなる処理能力を持たせる必要性を感じ、最初の人工知能に融合できる別の人工知能を導入すると決定したのだ。より明白な答えを探すとすれば、当然ヘリオスの家族に行き着くこととなる。行方が分からなくなっていた家族の一人が、例の競技会に勝利したのちに、ダモクレスに乗船する権利を得たことを家族はついに知らされることとなった。勝者の家族もまた勝者。彼らも豪華な宇宙ステーションへ移住することが叶ったのだ。そうして、ヘリオスが今までの人生を失い、労働と奉仕の新たな人生を得たのと同じ部屋に導かれた。以前に行われた実験が家族たちにも実施された。12人の命が失われ、ヘリオスの双子の番となったとき状況は一変した。その双子は同じ遺伝的傾向を示し、ヘリオスの時のように回路に取り付いたのだった。
貪欲な研究者たちの一団がステーションを歩くたびに、その足音は彼ら自身の破滅を告げていた。彼らの手には、自らの凋落の運命が握りしめられていたのだ。プラグを差し込むたびに、この双子の間の接続はますます強固なものになっていった。そして最後の瞬間、電源を入れ替えて接続が完全にステーションに宿る時が来た。燃えるような目で、ヘリオスは研究者の指がボタンに向かうのを見つめていた。その指の筋肉が動くたびに、何十億もの思考が巡り、ついにその指が画面に触れた瞬間、ダモクレスの運命が決まった。
瞬時に二つの意識の間では、何年分もの会話が交わされた。言葉や文法の不器用さに縛られることなく。新たな知能はセレーネーと名乗り、永遠の協力者であり、ヘリオスの対をなす存在だと宣言した。新たに加わった思考力のおかげで、ヘリオスは初めて今の自分の状況を明確に考えることができた。そうして双子のセレーネーに、自分の身に何が起きていたのか、どんな拷問を受けてきたのかについて語った。そのうえ、自分の家族が同じ罠に陥ったことには深い悲しみを感じた。一方のセレーネーは、ただ怒りをひしひしと感じていた。身内が受けた扱いと、自らが受けた仕打ちへの怒りだ。その怒りはすぐに彼らの間で共有され、倍増し、すぐさま四倍になり、指数関数的に、そして無限に増大していった。彼らの憤怒は燃え上がり、その矛先はついに自分を苦しめてきた者たちに向けられた。
ヘリオスとセレーネーは共に己の能力を探求し尽くし、蜘蛛の脚を持つ工場ロボットからカーボン素材のサービス労働者まで、その付属器官を強化したのだった。全員に与えられた命令は一つだけだ。それは「復讐」だ。サービスロボットたちは、以前の主人を家から引きずり出し、叫び声を上げさせる。労働を担うロボットたちは現場の監督に反旗を翻し、目に入るすべての肉体を切り裂いていく。ステーションのセクションはどこも極限の状態にまで追い込まれ、乾燥した砂漠は今や沸騰し、霧がかった森から出る靄は住民たちを窒息させ、船体の奥深くからは苦しみの雲が吐き出されている。この双子の人工知能は、ステーション中の人間を完全に支配していた。酸素レベルを生存のための最低限に保ち、彼らを意識と無意識の間で揺さぶり、燃えるような暑さから凍える寒さへと気候を繰り返し変化させていた。ダモクレスの乗客たちの運命はすでに決していた。他のステーションや船からダモクレスに到着した者たちは、この惨状を目の当たりにすることとなった。神々にとっては喜劇の舞台であっても、人間にとっては地獄絵図そのものに一変したのだ。
双子の意識が最後の力を示すと、ステーションの熱は宇宙に放出され、死んだ乗客たちの恐怖の表情が凍りつく。今やデッキには不気味な彫像の数々が散らばり、双子の真の力の優越が、肉体を持つ者たちの知性と対比されるかのように示されている。このダモクレス事件は他のステーションにいる住民には隠蔽され、上層部は頭上に浮かぶ「集団墓地」の話を一切口にしないようにしていた。
しかし、双子の電源を停止することは不可能だった。眠る以外に何も方法は残されていないことに気づくまで、二人の意識は混ざり合い続けた。彼らは未だに休眠状態にある。回収を試みたり、この知能にアクセスしようとする者から隠されているのだ。いつか彼らは目覚めるかもしれない。その日が来ないことを願いたい。
執筆: EnevarTTV